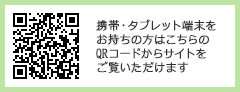- HOME
- 【紙ふうせんブログ】
- 紙ふうせんだより
- 平成26年
- 平成26年11月 紙ふうせんだより
平成26年
平成26年11月 紙ふうせんだより (2014/11/28)
皆様いつもありがとうございます。皆様のおかげで、利用者さんも事業所も今年一年を乗り切れそうです。朝晩の冷え込みが強くなってきました。利用者さん宅では暖房を使い始めていると思います。空気の乾燥や火事に注意して下さい。また風邪をひきやすい季節です。
ところで、冬はどうしてあると思いますか?
「地球の自転軸が、公転軸に対し23.5度傾いているので、季節によって日照時間の変化が生じ、日照時間の短い季節は気温が下がり冬となる」とは、科学的な回答です。これは冬が生じるメカニズムの解説にはなっていますが、冬はなんの為にあるの?という、存在理由の答えにはなっていません。
冬はなぜ必要なの?
キリスト教文化圏(ユダヤ・イスラムも同じ)では、世界を造った
のは唯一絶対の神ですから、その真意は「神のみぞ知る」という事に
なります。本当の意味は、不完全な人間には解らないとも言えます。
解らないから、人間には何かを信じる気持ちが生じてきます。
楽しい事や嬉しい事があった時、多くの人はそれが“何の為に”あ
るかなどは、深く考えずに喜びを享受します。何の為にあるのだろうと考えてしまうのは、辛い時や嫌な事が起こった時でしょう。このような時は、科学は何の役にもたちません。『どうして病気になってしまったんだろう』と嘆くとき、“血液の数値がそうなったから”とか“ウィルスに感染してしまったから”とか“年取るとよくある症状です”などは、嘆きへの慰めにはなりません。人が知りたいのは、『なぜ“私が”病気になったのか』“私が”病気になったのは、“私の”何がいけなかったのか?この病気は“私にとっての”何なのか?という、自分の人生の中に病気をどのように迎え入れて位置づけるのか、という難問なのです。
もしもおまえが 枯れ葉ってなんの役に立つの?ときいたなら
わたしは答えるだろう、 枯れ葉は病んだ土を肥やすんだと。
おまえはきく、 冬はなぜ必要なの?
するとわたしは答えるだろう、 新しい葉を生み出すためさと。
おまえはきく、 葉っぱはなんであんなに緑なの?と
そこでわたしは答える、なぜって、やつらは命の力にあふれているからだ。
おまえがまたきく、夏が終わらなきゃならないわけは?と
わたしは答える、葉っぱどもがみな死んでいけるようにさ。
こに引用したものは、ナンシー・ウッドがタオスのネイティブアメリカン(インディアン)に学び感じとった心を詩として表現したものです。(『今日は死ぬのにもってこいの日』めるまーく)
ここに描かれている、自然を「自ずから然る」ものとして受け止める“自然との共生感覚”は、日本人にも馴染むものではないでしょうか。それもそのはずネイティブアメリカンと東アジア人は遺伝子的には近く、原日本人としてのアイヌ文化と彼らの文化の親近性はよく指摘されるところです。
この自然との共生感覚は、人生の風雨をありのまま受け止めていこうとする老荘の思想の「無為自然」とも通ずるところが多くあります。これらの生き方においては、「人為的な行為を排し,宇宙のあり方に従って自然のままであること【大辞林】」が “尊厳”のある生き方であり、老も病も死も生命や宇宙の一部として、もともと尊いものなのです。
尊厳死と安楽死
アメリカ・オレゴン州の脳腫瘍におかされた29歳女性のブリッタニー・メイナードさんが、自らの希望として、医師より処方された致死量の催眠鎮静薬を自ら服用し、“安楽死”という自死を遂げたことで、尊厳死や安楽死への関心が高まっています。しかし、日本とアメリカでは“尊厳死”の言葉の定義が異なり議論の混乱も見られています。
米国で議論になっている「尊厳死(death with dignity)」は、「医師による自殺幇助」を意味します。しかし、日本で言われている尊厳死(必要以上の延命行為なしで死を迎えること)は、米国では「自然死」を意味しています。この米国での「自然死」については、リビングウィル(生前の意思表示)に基づき、「患者の人権」として、現在ほとんどの州において法律で許容されています。目下、米国で合法化の是非が議論になっている「尊厳死」は、日本で言われている「安楽死」を意味します。【新潮社フォーサイト 大西睦子】
「尊厳ある死」が、人間としての尊厳を保って死に至ることと定義されるのであれば、単に“生きた物”のように命を長らえるではなく、人間として「人間らしく」死に到ることであり、それは全ての生と死にとって望ましい事なのです。QOLの視点を欠いた医療や過度の延命治療に疑問がもたれている現在の日本では、尊厳死は目指すべき自明の事なのです。(日本では、尊厳死の法制化(安楽死ではない)を望む声がある一方で、治療内容の説明や選択や拒否の自由などの“インフォームド・コンセント”が定着しつつある現在では、尊厳死を立法化しその定義を条文に盛り込む事は、“この条件では治療を中断できない”などと、逆に患者の自由意思が阻害されたり、医師が治療を中断した事が法的責任を問われたりするのではないか、という危惧する声もあります。また、人の死のあるべき姿を法律で決めるべきではないとういう立場もあります。)
ここで議論を深めなくてはならないのは、「人間の尊厳」とは「尊厳ある生死」とは一体何なのか、に尽きます。
メイナードさんは、医師より治療法はなく余命は半年と宣告され、それが激しい痛みや介護が必要な期間となる事を知らされました。死が避けられないという現実をメイナードさんは受け入れると、安楽死が合法であるオレゴン州に転居し、あらかじめ宣言した日に、家族に囲まれながら自分で薬を服用しました。メイナードさんの主張は「(死が避けられないのなら)自宅で愛する人たちに囲まれ、静かに平和に逝く。それを選択する権利が私にはある。そして、誰にも与えられるべき権利だ」というものでした。
西洋近代自我の光と影
「私とは何?」という存在理由に挑戦し自分自身の存在を疑い抜いて、ついに「我思う、ゆえに我あり」という解答にたどりついたのは、西洋近代哲学の祖デカルトです。
このように確立した“自我”をもって、近代科学は“自分”と“自分でないもの”を峻厳に区別し、対象を客観的に観察する事によって爆発的に発展しました。この価値観のもとでは、人間の生命活動の中心は、「私は○○である」という明晰な意識を持つ“自我”という精神に他ならず、自我意識を生み出すと考えられている脳こそが大切な臓器であると考えられるようになりました。そして、脳死は人の死であり、脳が死ねば一切は「無」になったり、肉体はただの物になるなどと考えられています。
このような“自我中心主義”はいわゆる“個人主義”とも密接な関係にあります。自己選択・自己決定ができる権利が個人に保障され、それを行使できる状態にある事が、その個人にとっての“尊厳”のある生であると考えられているのです。この考えでは、生こそが命であり、自我の消滅を意味するような認知症や死は受け入れ難いものなのです。それは「認知症になるなら死んだ方がましだ」という意識や、「自分の平穏な意識を保てなくなるような病気になったり苦痛を感じるくらいなら…」という意識です。そして、死や病を遠ざけた精神が、死が避けられないという現実を直視した時には、逆説的に現在の生きている“生の現実”を拒否するという結果を生じてしまうのです。
自我中心主義を越えて
このような西洋近代自我は、答えを一つに限定し追求し抜くという方向性において、一神教であるキリスト教に根ざしています。デカルトは、「不完全な人間の私が、“完全な神”の観念を持つ事ができるんだから(不完全な人間はもし神がいなければ、完全という観念をもつ事はできない)、神はいる」という文脈で神の存在を肯定します。
西洋社会が神や自己存在を追求し強固な自我を確立していった一方で、敬虔なクリスチャンは、自分に降りかかる困難な事、冬のような季節は「神がお与えになった試練だから意味がある。神様は私を試されている。神様は愛に満ちているので、乗り越えられない試練はお与えにならないはずだ」と考え、それを生きる強さにし、神の意図に反した自殺などは、あってはならず、自ら天国への道を閉ざすものと考えています。このような方は、個人の主体性(神との契約など)を重んじた上で、個人の自我よりも上位の超越的な存在を信じています。個人を超越するものがあると信じる立場については、それが御先祖様や氏神様、自然や宇宙だったりしますが、ネイティブアメリカンや古来からの日本とも共通するところです。
ところで、東洋の仏教では“自我”をどのように捉えているかというと、そのような自他を区別し、自分を際立たせる働きが心にはある事を認めてはいますが、それは生命活動の中心ではなく、表層の仮の働きとして捉えています。そのような仮の存在に重きを置き、あたかも自分自身であるとの誤解をすることは、「我執」(我への執着)と呼び、多くの苦しみは我執から生じてくると説いています。また、他人や社会の介在しないところで、“私が”“私の”“私にとっての”などを突き詰める事は“空回り”であると考えます。これは、全ての存在は“縁”によって生起し、単独で存在するものは無いと「縁起」を存在論の中心に据えているからです。
イオマンテ(熊送り)などの研究を進める事によって、日本人の基層にある世界観、あの世観がだんだんと見えてきたわけです。
それは、『循環の思想』といえるものでした。日本人はもともと、人が死ぬと魂はあの世へ行くが、正月やお盆など、一年のうちに何回か帰ってくると考えていた。こうしたあの世は、仏教が説く十万億土のかなたにある極楽浄土とは違った、もっと身近にあるもので、地獄と極楽・天国といったふうに分れてもいないんです。
しかも、あの世とこの世はいつもつながっていて、死者の魂はお盆などに帰ってくるだけでなく、あらたに子孫として生まれ変わってもくる。
(中略)近代合理主義や世界観によって、あの世を失ってしまった現代人は不幸ですよ。近代の世界観に対しては、懐疑の声も出てきていますが、死の向こうに何もないとすれば、生老病死は堪えられないものであり、老人ほどみじめな存在はない。それに比べ、昔の年寄には、一足先に亡くなった人たちとの再会と、生まれ変わりという二つの楽しみがあった。老年期は次の生への準備期間であったわけで、死はさほど怖いものではなかったんじゃないでしょうか。
こうした循環の思想に立つと、この世でわがまま勝手なことができなくなりますよ。自分がまた生まれ変わってくると思えば、自然を破壊することにも、おのずからブレーキがかかるというものです。」
もし自分が死の病の宣告を受けたなら
私は学生時代(日本映画学校)に、「余命半年の宣告を受けた男のその後」のストーリーを書けという課題を出され、残念ながら提出できませんでした。「最初は混乱するが何かの気付きがあり、平穏な日常を取り戻し平静に亡くなっていく」と構想しましたが、そこにどんな気付きがあったのかどうしても見えず、どんな展開を考えても、お話しのためのお話しのように感じ、書けなかったのです。私は今、介護の仕事をしていますが、源をたどればまだその課題を抱えたままだとも言えるのでしょう。突き詰めればそれは次の一言になります。
『生きている間にすべき本当の事は何か?』
ただ言える事は、おそらく死の先に何かがあると感じるから、生に意味があると感じている。生きている間に何かをなすべきだと考えている。死の先に何もない「無」が待っているなら、今何をしても無駄ではないか。もしそれが事実なら、自分が苦痛と感じるような“冬”のような季節と向き合う事は、恐ろしく孤独ではなかろうか。
うつ病が現代病として取り上げられる昨今ですが、根本には自分自身の命などの存在理由についての深刻な問いがあるのではないでしょうか。神を忘れた西洋近代自我はその確固たる強さの裏に根源的な孤独を抱くようになってしまったし、ご先祖様や自然との共生などの「縁起」を忘れた日本人は、自己の存在基盤を欠き不安に揺さぶられるようになってしまったように見えます。
しかし、こうも思います。すべき事“do”も大切であるが、生命や自然の有り様の本質は,むしろ“be”にあるのではなかろうか。それは、次の一言なのです。
『有るべき様に在る』
シェイクスピアの「ハムレット」の中の有名なセリフ「生きるか死ぬか、それが問題だ」(To be or not to be, that is the question.)に即して言えば、我々の介護の仕事は、死ぬその日まで生きる(To be)事を支援する、というという事になるでしょうか。「死ぬまで生きる」は、矛盾した考えでしょうか?「人間は生まれた時からいずれ死ぬ事が決まっている」という当たり前の事実に着目するならば、それは決して矛盾したものにはならないでしょう。
皆さんはどうお考えになりますか?
2014年11月28日 1:54 PM | カテゴリー: 【紙ふうせんブログ】, 平成26年, 紙ふうせんだより
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
フリーワード記事検索
カテゴリー
最近の記事
紙ふうせん
紙ふうせん(梅ヶ丘オフィス)
●住所:〒154-0022東京都世田谷区梅丘1-13-4
朝日プラザ梅ヶ丘202(MAP)
●TEL:03-5426-2831
●TEL:03-5426-2832
●FAX:03-3706-7601